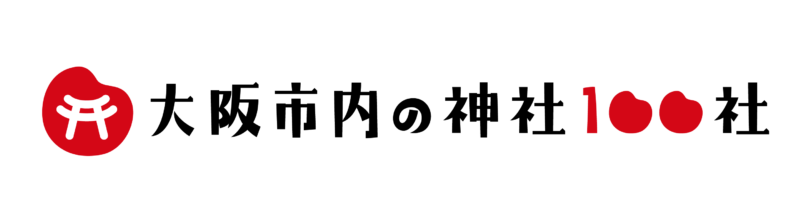空海も祈願した?!澪標住吉神社での静かな時間(みおつくし神社)【大阪市・此花区】

澪標住吉神社(みおつくし神社)【大阪市・此花区】
大阪市・此花区の静かな町にひっそりと佇む「澪標住吉神社(みおつくしじんじゃ)」。
「澪標(みおつくし)」という美しい名前は、航路の目印として海に立てられていた標柱からきており、海とともに歩んできたこの神社の歴史を物語っています。
そのはじまりは平安初期ともいわれ、あの空海も遣唐使として出発する前に、航海の安全を願って立ち寄ったという伝承も。地元の漁師たちはその祈りに心を動かされ、小さな祠を建てて大切に守ってきました。
現在は静かな住宅街にある澪標住吉神社ですが、その空間には今もおだやかな風と、昔ながらの信仰が息づいています。
そっと立ち寄り、心を落ち着けたいとき。澪標住吉神社で、日々の小さな願いを込めて深呼吸してみてください。ご利益とともに、心を癒してくれるひとときが、きっとそこにあります。
海の神様に見守られて。澪標住吉神社で、静かに願いをかけるひととき
海に寄り添う町・伝法に、ひっそりとたたずむ澪標(みおつくし)住吉神社。
「みおつくし」という美しい名前は、航路のしるしとして海に立てられた“澪標”にちなんでつけられたものなんです。
空海も見上げた?歴史は1000年以上
創建は定かではありませんが、その歴史はおよそ600年前以上とも。
そのルーツを辿ると、時は平安初期の西暦804年。遣唐使として出発する一行(その中にはあの空海の名も)が、
出航前にこの地に立ち寄り、住吉の神様に航海の安全を祈願したと伝えられています。
この地に住んでいた漁師たちはその祈りに心を打たれ、小さな祠(ほこら)を建て、
やがて帰ってくる一行のために、海の中に澪標(みおつくし)=航路のしるしを立てたのだとか。
静かな島の神様から、港町の守り神へ
もともとこの場所は“浪華八十島”のひとつ。
白い砂浜と緑の林に囲まれた小さな島にすぎませんでしたが、豊臣秀吉の時代になると風向きがガラリと変わります。
大阪城の築城にともなって、この地は「伝法口」と呼ばれる湾内の重要な港へと成長。
美味しい水にも恵まれ、やがて酒造が盛んになり、江戸や北海道まで酒が運ばれるようになったといいます。
航海の安全と豊かな暮らしを願って
時代が進むにつれて、地域の人々はこの神社を航海と商売繁盛の神様として、ますます深く信仰するようになりました。
船主たちは、長旅から無事帰るたびに、感謝の気持ちを込めて帆柱を奉納し、それが鳥居の材料になったというエピソードも。
浜辺には大きな澪標と二基の石灯籠が並び、赤い大鳥居が空と海に映えていたそう。
その美しさは、今も地元の方の記憶に残っているそうです。
おだやかな時間が流れる、街の隠れ神社
静かな住宅街にある澪標住吉神社。
喧騒から少し離れて、ふっと深呼吸したくなるような、心地よい空気が流れています。
「何かを始めたい」「迷いを晴らしたい」そんな時には、海と歴史に守られたこの場所で、そっと願いをかけてみてください。
会社帰りや週末のお散歩に、ちょうどいい距離感の小さなパワースポットです♡
- 住吉大神
- 天照皇大神
- 八幡大神
- 神武天皇
- 神功皇后
神社巡りをされる方へ|御朱印帳の選び方ガイドはこちら