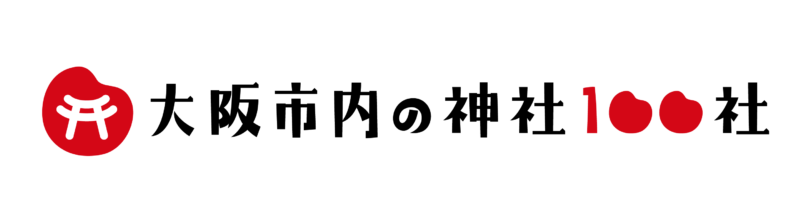木津川そばの津守神社で歴史と癒しにふれるさんぽ旅【大阪市・西成区】

津守神社【大阪市・西成区】
大阪市西成区にある津守神社は、木津川のほとりに静かにたたずむ、やさしい空気に包まれた神社です。地元では「津守さん」として親しまれ、季節の風を感じながら心を整えられる場所として、多くの人に愛されています。
境内にある「狸灯篭」は、夜になると不思議な光を放ったという言い伝えも残る、ちょっとユニークな存在。小さな神社ながらも、地域の歴史や伝説がしっかりと息づいています。
都会の喧騒からほんの少し離れて、深呼吸できるひとときが過ごせる津守神社。西成区を歩くなら、ふらっと立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
木津川のほとりで、ちょっとひと息「津守神社」へ
大阪・西成区の津守エリアに、地元の人たちに親しまれている神社があります。
名前は「津守神社」。かつて新田開発でにぎわったこの地域で、静かに地域を見守り続けてきた、やさしい鎮守さまです。
川風を感じながら、おだやかな空気に包まれて。
ちょっとだけ日常から離れて心を整える、そんなお出かけにもぴったりな場所です。
始まりは、新しい土地への願いから
津守神社の歴史は、元禄時代にさかのぼります。
当時、木津川の河口にできた新しい土地・津守新田の開拓を進めていた京都の商人・金屋源兵衛が、
新田の守り神として天照大神と稲荷大神をお祀りしたのがはじまりです。
土地の開発と人々の暮らしの安全を願い、神さまを迎え入れて祈りを捧げた…
そんな真摯な想いから、この神社は生まれました。
時代とともに移り変わる、まちと神社
江戸時代から明治、大正、昭和と、津守神社は地域の移り変わりとともに姿を変えながらも、
常に人々の暮らしのそばにありました。
明和6年(1769年)には現在の場所へ遷座され、社殿や手水舎、絵馬殿などが整備。
そして昭和初期には大風水害により大きな被害を受けましたが、地域の人々の支えで立派に復興されました。
伝説も残る、津守の「狸灯篭」
境内にはちょっとユニークな見どころも。
そのひとつが「狸灯篭(たぬきとうろう)」と呼ばれる変化灯篭。
夜になると不思議な光を放ったり、姿が変わるという伝説が残されていて、
今も摂津の名物のひとつとしてひそかに語り継がれています。
今も変わらず、地域とともに
戦火を免れ、戦後は宗教法人として再出発した津守神社。
氏子や講社のみなさんの支えによって守られ、今でも月次祭やさまざまな行事が丁寧に続けられています。
地域の人たちにとって、生活の中に自然と溶け込む存在。
ふらっとお参りして、心がほっと落ち着く…そんな場所です。
近くに来たら、ぜひ足を運んでみて
都会の中にありながら、どこか懐かしくて、やさしい空気に包まれた津守神社。
お散歩ついでにふと立ち寄れば、少しだけ時間がゆっくり流れるような気持ちになります。
木々の緑に囲まれた境内で、深呼吸。
今日の疲れをそっと癒してくれる、そんな小さな神社です。
- 天照大御神
- 稲荷大神
- 大歳大神
- 住吉大神
- 綿津見大神
神社巡りをされる方へ|御朱印帳の選び方ガイドはこちら