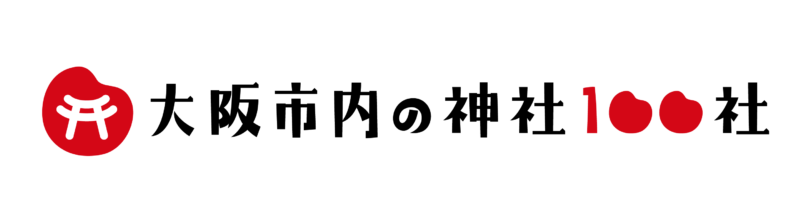心を整える川辺時間 – 平野区の川辺八幡神社へ【大阪市・平野区】

川辺八幡神社【大阪市・平野区】
川のせせらぎと季節の風に包まれて、ちょっと気持ちを整えたいとき。そんなときにふらりと訪れたくなるのが、大阪市平野区にある川辺八幡神社です。
大和川の堤防沿いにひっそりと佇み、地域の暮らしにそっと寄り添うこの神社は、長い歴史と共に受け継がれてきたご利益のある祈りの場所。
かつては石清水八幡宮のご分霊を勧請し、「若宮八幡宮」として親しまれていたこの神社。後醍醐天皇や楠木正成とのご縁、そして大和川の流れに運ばれて今の地に根づいた歴史が、境内の静けさの中に息づいています。
お散歩の途中で、通りすがりに、ふと深呼吸したくなったら。川辺八幡神社で、心静かなひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。
堤防の上のやすらぎ空間、川辺八幡神社へ
大阪の南端を流れる大和川。そのすぐそば、大和川の堤防北側に、
ひっそりと佇むのが「川辺八幡神社」です。
川のせせらぎを感じながら、季節の風に吹かれて歩くお散歩道。
その途中で出会える、心がほっとするような神社です。
はじまりは石清水八幡宮のご分霊から
この神社の創建時期ははっきりとは伝わっていませんが、
そのはじまりは石清水八幡宮のご分霊を勧請したことにあると言われています。
かつては「若宮八幡宮」と呼ばれ、地域の守り神として大切にされてきました。
歴史の中で守られてきた祈りの場所
後醍醐天皇から宸翰を賜り、楠木正成公からは菊水の旗が奉納されたという伝承もあり、
その昔、ここがいかに大切な場所だったかがうかがえます。
当時の社領はなんと約400町歩(1町歩=約9,900㎡!?)。現在の規模からは想像もつかないほど広大で、
末社には少彦名神社や厳島姫神社があったとされています。
川の流れとともに、今の場所へ
宝永元年(1704年)、大和川の付け替え工事によって元の社地の多くが川底に沈み、
現在の場所へと移されました。
その際、堤防の上にはお旅所も築かれ、川とともに歩んできた神社の歴史が今も息づいています。
静かな時間が流れる境内
明治五年には今の社地が整えられ、大正時代には本殿や拝殿、手水舎、社務所も整備。
今では、金𠮷稲荷神社や歯神社といった末社も並び、地域の人々の祈りが重ねられています。
昭和二十七年には「川辺八幡神社」と社名を改め、今もこの地の氏神さまとして愛されています。
川辺で深呼吸。日常に、ちいさな旅を
何かと忙しい日々の中でも、ふと足を止めて立ち寄りたくなる、川辺八幡神社。
川風に吹かれて歩いた先で、心静かに手を合わせてみませんか?
季節ごとに違った表情を見せてくれるこの場所で、
ゆったりとした時間を過ごしてみてはいかがでしょう。
- 品陀別命
神社巡りをされる方へ|御朱印帳の選び方ガイドはこちら