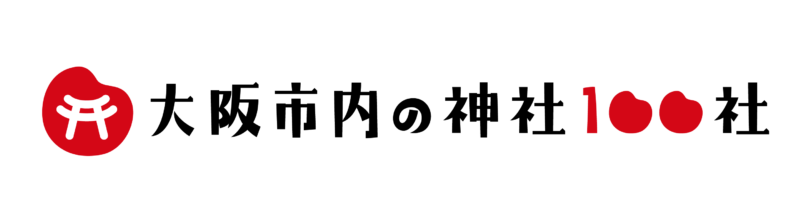湯里の住吉神社で出会う心落ち着くおさんぽ時間(湯里住吉神社)【大阪市・東住吉区】

住吉神社(湯里住吉神社)【大阪市・東住吉区】
東住吉区の湯里にひっそりと佇む「住吉神社」は、地元で「湯里の住吉さん」として親しまれている神社。喧騒から少し離れた町並みに、ふと心がほっとする静けさが漂っています。
この地に祀られるのは、中筒男命(なかつつのおのみこと)。
かつて「住吉二の宮」とも呼ばれたこの神社は、商売繁盛や五穀豊穣のご利益があるとされ、古くから人々の暮らしを支えてきました。
境内にある大きな楠の木は、神さまが宿る神木として大切にされ、かつて“お告げ”があったという伝承も残されています。
忙しい日常のなかでも、少しだけ時間をゆるめて立ち寄ってみたくなる、そんなやさしい神社です。
湯里のまちに佇む「住吉さん」で、心静かなお散歩時間を
東住吉区・湯里町。昔ながらの街並みのなか、そっとたたずむ「住吉神社」は、地元の人からは「湯里の住吉さん」と呼ばれ、親しまれてきた神社です。
喧騒から少し離れて、ゆったりと歩きたくなる道。
ふと立ち寄るだけで、心がすっとほどけていくような、そんな空気がここにはあります。
神さまとのご縁は、ずっと昔の「天神山」から
この神社のルーツは、さらに南にあった「天神山」という丘の上。
かつてこの地域一帯を治めていた「富田荘」の守り神を分けて、この地に祀ったのがはじまりといわれています。
祀られているのは、住吉大社でもおなじみの中筒男命(なかつつのおのみこと)。
そのため、昔から「住吉二の宮」とも呼ばれていたそうです。
街の移ろいとともに、静かに守られてきた場所
何度かの火災や戦乱もあり、古い記録は焼失してしまったものの、住吉神社は地元の人々の信仰に支えられてきました。
明治時代には「村社」として指定され、大正・昭和にかけて少しずつ整備されていきます。
石玉垣や社務所が整えられ、参道には石畳も敷かれ、神社らしい凛とした空気が広がっています。
境内の大きな楠と、ふしぎなお告げ
境内の南東に立つ大きな楠(くすのき)は、神さまが宿るとされており、かつて「お告げ」があったという話も残っています。
その出来事をきっかけに、人々の手によって小さな「楠社」も建てられました。
目を閉じると、風に揺れる木々の音や、どこか懐かしい鳥の声が聞こえてきそうです。
日々の中で、ふと訪れたくなる神社
お買い物の帰り道に、ちょっと気分を変えたい時に。
湯里の住吉さんは、日常のなかにそっと寄り添ってくれるような、そんな存在です。
昔からまちの人たちの願いを受けとめてきた、穏やかな神さまに会いに、ちょっとだけ足を伸ばしてみませんか?
- 中筒男命
- 商売繁盛
- 五穀豊穣
神社巡りをされる方へ|御朱印帳の選び方ガイドはこちら