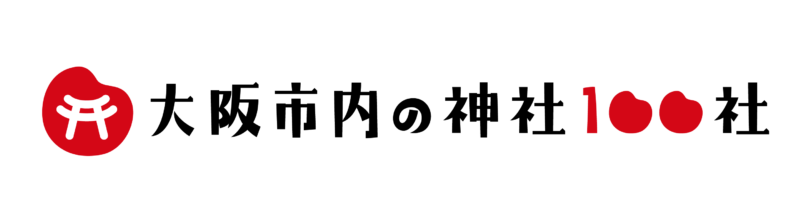長居の歴史に出会える癒しの神社 – 保利神社の魅力(長居の宮)【大阪市・住吉区】

保利神社(長居の宮)【大阪市・住吉区】
大阪市住吉区の住宅街にひっそりと佇む、保利神社(長居の宮)。地元では“長居の宮”の名で親しまれてきました。
かつて「牛頭天王社」と呼ばれていたこの神社は、室町時代に武士たちの手によって創建されたと伝わり、歴史ある“堀村”の一角にありました。
境内には、大巳貴命も合祀されており、さまざまな願いに寄り添ってくれる存在です。近くには長居公園や植物園もあり、お散歩の途中に気軽に立ち寄れる“癒しスポット”。
日常の中でちょっと立ち止まって、自分と向き合いたい時。保利神社は、そんな時間を静かに支えてくれる場所です。
長居エリアで出会う、歴史の奥に佇む「保利神社」
静かな住宅街を歩いていると、ふっと現れる木々に包まれた神社。
ここは長居の地で“長居の宮”とも親しまれている保利神社(ほりじんじゃ)です。
地元の人たちが大切に守り続けてきたこの神社には、歴史ある由緒と土地の記憶がたっぷりと息づいています。
“堀村”と呼ばれた、城のような集落
神社のあるこの場所は、かつて「堀村」と呼ばれていました。
その名の通り、集落のまわりにぐるりとお堀をめぐらせた“小さな要塞”のような村だったのだとか。
伝承によれば、室町時代にこの地を築いた武士が、守り神として神様をお招きしたのがはじまり。
お堀の内側には竹薮も植えられ、ちょっとしたお城のような風景だったそうです。
かつての名は「牛頭天王社」
当初は素盞嗚尊(すさのおのみこと)をお祀りし、「牛頭天王社(ごずてんのうしゃ)」という名で親しまれていました。
厄除けの神様として、地域の人々の健康や暮らしを見守ってこられたのですね。
明治になると、「保利神社」と名前を改め、
さらに前堀村にあった吉山神社(ご祭神は大巳貴命)を合祀して、より多くのご神徳をもつ神社へと変わっていきました。
「長居」の歴史にもふれてみよう
近くにはかつて「追分茶屋」と呼ばれた交通の分岐点があり、
堺や住吉方面へ向かう旅人たちが行き交う賑やかな場所だったそう。
今ではすっかり住宅街となったこのエリアも、歴史をさかのぼれば
武士の村、旅人の道、そして神さまの鎮まる地だったことがわかります。
平成の時代に生まれ変わった本殿
今の社殿は、平成10年(1998年)に氏子さんや崇敬者の浄財によって新たに建て替えられたもの。
明るく、どこかやさしい雰囲気が漂う境内には、日常の中にある“ほっとする神社”という言葉がぴったりです。
気軽に立ち寄れる“長居の癒しスポット”
お散歩の途中、気分転換に立ち寄ってみたくなる保利神社。
古の記憶と、地域の温かさがほどよく交差する場所です。
「今日はちょっと、神社に寄り道してみようかな」
そんな気持ちのときにぴったりな、ほっこり神社です。
- 速素盞嗚尊
- 大巳貴命
- 厄除け
- 子孫繁栄
- 家内安全
神社巡りをされる方へ|御朱印帳の選び方ガイドはこちら