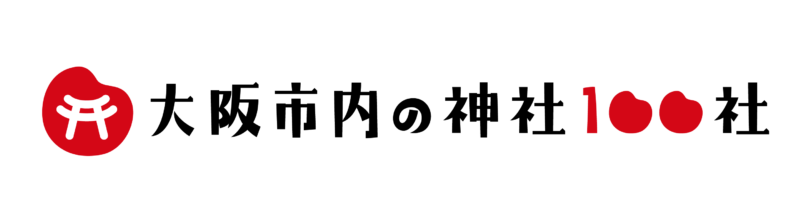柴に乗って流れ着いたご神体から始まる物語 – 柴島神社で癒しのひととき【大阪市・東淀川区】

柴島神社【大阪市・東淀川区】
大阪市東淀川区にある柴島神社は、水のまち・柴島に静かに佇む、やさしさに満ちたお社です。鎌倉時代、淀川の大洪水の際に柴の束に乗って流れ着いたご神体が祀られたことからはじまり、地域の人々と深いご縁で結ばれてきました。
“柴島”という地名の由来にもなったとされるこの神社では、八幡大神・天照大神・春日大神の三柱の神様が、今も変わらず暮らしを見守ってくれます。
歴史ある神社で手を合わせれば、家内安全や商売繁盛などのご利益に加えて、心にやさしい静けさが広がりますよ。日常の合間に、ふっと一息つきたくなったら、ふらりと立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
水辺のまち・柴島にひっそりと佇む神社
大阪・柴島(くにじま)の住宅街を歩いていると、静かにたたずむ「柴島神社(くにじまじんじゃ)」が現れます。
地元の人たちに長く愛されてきたこのお社は、ちょっと特別な“ご縁”で生まれた神社なんです。
のんびりした空気が流れる境内は、都会の喧騒を忘れて心がふっと軽くなるような場所。
「なんだか疲れたな…」という日に、ひとりでそっと立ち寄りたくなる、そんな神社です。
はじまりは、柴の束に乗って流れてきたご神体!?
柴島神社のはじまりは、なんと鎌倉時代までさかのぼります。
1232年、淀川の大洪水で町が水に沈んだある日…。高台に避難していた村人たちのもとに、柴の束に乗った小さなお社が流れ着いたのだそう。
中をのぞくと、そこには八幡大神、天照大神、春日大神の三柱の神さまが。
村の人々はその偶然の出会いに感謝し、大切に祀ったのが「柴島神社」のはじまりと伝えられています。
長い歴史をたどる、お引越しの記録
元々は淀川のそばにあった柴島神社ですが、明治時代の河川改修によって今の場所へお引越し。
その際、近くの仲哀天皇社も一緒に合祀されました。
時代の流れとともに移り変わる景色のなかでも、ずっと変わらず柴島のまちを見守り続けているんです。
“柴島”の名前のルーツにもなった神社
今では当たり前に呼ばれている「柴島(くにじま)」という地名も、実はこの神社が由来のひとつとされています。
「柴を久爾(くに)」と読む古い言葉からきているという説もあり、
神社とまちの名前が深く結びついているなんて、ちょっと素敵ですよね。
川とともに生きる、まちの誇り
この地域は昔から“晒し布”で有名で、「柴島晒(くにじまさらし)」として知られていました。
清らかな水と人々の営み、そして柴島神社の存在が、まちの歴史と文化をそっと支えてきたのです。
静けさに包まれて、ちょっとひと息
今の社殿は昭和41年に建てられたもの。
歴史の重みを感じつつも、どこか優しい空気が漂う境内で、
「もう少しだけがんばってみようかな」そんな気持ちが湧いてくるかもしれません。
いつもは通り過ぎてしまうような日常のなかに、そっと寄り添ってくれる柴島神社。
お散歩の途中で、ちょっとだけ立ち寄ってみませんか?
- 八幡大神
- 天照皇大神
- 春日大神
- 家内安全
- 厄除開運
- 商売繁盛
神社巡りをされる方へ|御朱印帳の選び方ガイドはこちら