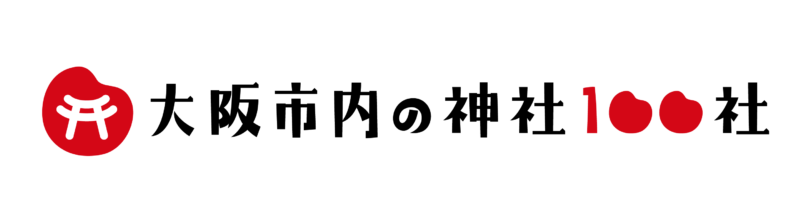七曲りの伝説が残るまちへ – 須佐之男尊神社で心ほどける散歩時間(関目神社)【大阪市・城東区】

須佐之男尊神社(関目神社)【大阪市・城東区】
大阪市城東区にある須佐之男尊神社(通称:関目神社)は、戦国時代から関目のまちを見守ってきた、歴史深い神社です。
豊臣秀吉の時代に鬼門除けとして祀られたのがはじまりで、七曲りと呼ばれる道の防御拠点にもなっていたとか。水害や風害を乗り越えながらも、地域の人々に支えられ、今もその姿を残しています。
境内はこぢんまりとしていながらも落ち着いた雰囲気で、明治天皇がご休憩された由緒ある場所としても知られています。
ご祭神は須佐之男尊(すさのおのみこと)。災い除けや地域安泰のご利益があるといわれ、地元では“関目の守り神”として親しまれてきました。
街なかにいながら、ふと歴史にふれられる関目神社。お買い物の途中やお散歩がてら、心静かな時間を過ごしてみてはいかがでしょうか?
街角の歴史と出会える場所。関目の守り神・須佐之男尊神社へ
大阪市城東区・関目の住宅街にひっそりとたたずむ、須佐之男尊神社(通称:関目神社)。
地元の人たちに愛され続けるこの神社は、豊臣秀吉の時代から続く、歴史あるお社なんです。
駅から少し歩けば、ふと現れる鳥居。
その先にある静かな境内は、喧騒を忘れられる癒しの空間です。
七つのカーブが語る、戦国時代の知恵と守り
この神社の始まりは、戦国時代。天正八年(1580年)、豊臣秀吉が大阪城を築いたころ、
敵の侵攻に備えて関目あたりの道をぐねぐねと曲げて作ったのが「七曲り」。
その防備の要となる場所に、鬼門除けの神様として昆沙門天王・牛頭天王(ごずてんのう)を祀る小さなお社が建てられたのがはじまりです。
それがのちに「須佐之男尊神社」と改称され、今に続いているんです。
水害・風害を乗り越えて。関目の人々とともに歩んだ神社
正徳の時代には強風で社殿が大きな被害を受け、さらに明治十八年の大洪水では社殿ごと流されてしまったことも。
それでも、地域の人たちが協力して再建を重ね、神様を守ってきた歴史があります。
境内には、創建当時に盛土を採った跡といわれる「連池」も残っており、昔の景色を今に伝える静かな佇まいが魅力です。
明治天皇も立ち寄った、由緒ある場所
実はこの神社、明治天皇が関目を巡幸された際にご休憩された場所としても知られています。
その記念に、地元の有志が「明治天皇御輩碑」を建立し、今も毎年7月に記念祭が行われているんです。
ただの街角の神社、と思いきや、地域の歴史がぎゅっと詰まった大切な場所なんですね。
近場のお散歩コースに、ぴったりの小さな旅先
都会の中にあるのに、どこか懐かしくてほっとする空気感。
関目エリアでのお買い物帰りや、カフェタイムの前後など、ふらっと立ち寄れる“心のよりどころ”として、ぜひ足を運んでみてください。
戦国の知恵・自然の力・人の想いがつながった場所で、あなたも静かな“ときの旅”を楽しんでみませんか?
- 須佐之男尊
須佐之男尊神社(関目神社)
地下鉄谷町線関目高殿駅から徒歩5分
地下鉄今里筋線関目成育駅から徒歩5分
神社巡りをされる方へ|御朱印帳の選び方ガイドはこちら