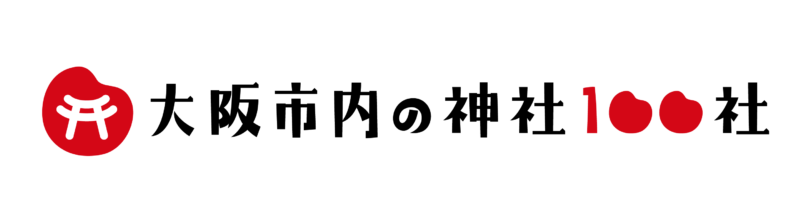水と木とご縁の神さまに会える – 住之江のやさしい高崎神社 高崎神社【大阪市・住之江区】

高崎神社【大阪市・住之江区】
町のにぎわいから少し離れた住之江区の住宅街に、そっとたたずむ「高崎神社」。
天保の時代から地域を見守りつづけてきたこの神社は、
水の神さまや自然の神さまをお祀りし、五穀豊穣や縁結びなど多彩なご利益で知られています。
華やかさよりも、ぬくもりとやさしさを感じる境内は、
日常に疲れたときや、ふと心を整えたくなったときにぴったり。
お散歩の途中、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょう?
静かな町の一角で、ほっとひと息つける場所に出会えますよ。
町のはじっこ、やさしく迎えてくれる「高崎神社」へ
大阪・住之江エリアの静かな町角に、そっと佇む「高崎神社」。
華やかさはないけれど、なんだかほっとする。そんな“街のよりどころ”のような神社です。
駅からちょっと足を伸ばして、お散歩がてら立ち寄ってみると、
忙しい日常の中で忘れていた「心の余白」を思い出させてくれます。
埋立ての祈りから生まれた神さま
高崎神社がこの地に祀られたのは、天保10年(1839年)のこと。
町の開発を進めていた加賀甚兵衛さんが、度重なる洪水や高潮に悩まされ、
生まれ故郷の氏神・水分社の神さまに「この土地をどうか守ってください」と願いを込めてお祀りしたのが始まりです。
やがて工事は順調に進み、現在の住之江から西成にかけて広がる大きな土地が完成。
それ以来、この神社は五穀豊穣や縁結び、地域の守り神として、大切にされてきました。
雨乞いから飛行場まで? 変わりゆく町を見守って
この神社には、かつて雨乞いの神さまとして祈られた歴史も。
長く続いた日照りの中、村人が祈りを捧げたところ、まるで願いが届いたかのように恵みの雨が降り、
綿花の豊作につながった…というエピソードも残っています。
昭和に入ると、この土地は軍の飛行場としても利用されるように。
開発や時代のうねりのなかでも、神社は変わらずに、地域の人たちの心の支えであり続けました。
神さまたちのご紹介
高崎神社でお祀りされている神さまは三柱。
- 天之水分大神(あめのみくまりのおおかみ)…水の恵みと命の循環を司る神さま
- 大物主大神(おおものぬしのおおかみ)…国づくり・縁結び・商売繁盛の神さま
- 久々能知大神(くくのちのおおかみ)…木や森を守る自然の神さま
どの神さまも、日々の暮らしのなかで「ちょっと助けてほしいな」と思うときに、
そっと背中を押してくれるような存在です。
今も、町のまんなかで変わらずに
昭和・平成・令和と時代が移っても、神社は地域の行事や祈りの場として大切にされています。
お祭りのたびに賑わう境内、静かな朝の参拝、そして地域の人々の語らいの場。
そんな「人と人とをつなぐ場所」として、今日も変わらず、街を見守っています。
アクセス
住之江区・南港通りから少し中に入った住宅地のなか。
周辺には南港や平林公園もあり、のんびりした休日のお散歩コースにぴったりです。
心がふっと軽くなるような時間を求めて、あなたも一度、訪れてみてはいかがですか?
- 天之水分大神
- 天照皇大神
- 柿本人丸大神
- 五穀豊穣
- 縁結び
高崎神社
南海本線七道駅から徒歩14分
南海本線住ノ江駅から徒歩17分
神社巡りをされる方へ|御朱印帳の選び方ガイドはこちら