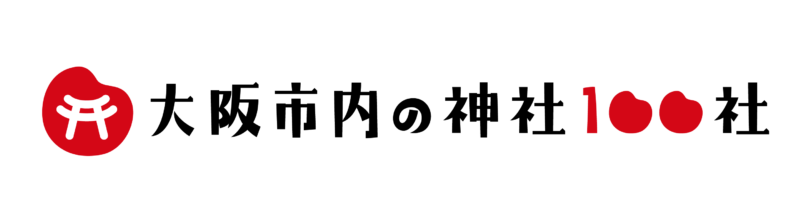歴史と海の記憶が息づく田蓑神社でご縁を感じて【大阪市・西淀川区】

田蓑神社【大阪市・西淀川区】
大阪市西淀川区にたたずむ田蓑神社は、川風が心地よい住宅街の一角にある、静かであたたかなお社。地元では「田蓑さん」の愛称で親しまれ、古くから暮らしに寄り添ってきました。
創建は平安時代。神功皇后と漁師との心温まる出会いがはじまりとされ、住吉三神とともにご祭神として祀られています。ご利益は商売繁盛や交通安全、厄除けなど、日々の願いにそっと寄り添ってくれる内容ばかり。
震災で傷つきながらも、地元の人々の力でよみがえった境内は、今も変わらず穏やかで、やさしい時間が流れています。
西淀川区をおさんぽする日に、心を整えるひとときとして、田蓑神社をふらりと訪れてみてはいかがでしょうか。
川風を感じる町に佇む、やさしい住吉さま
大阪・西淀川区の静かな住宅街に、ひっそりとたたずむ「田蓑神社(たみのじんじゃ)」。
地元では“田蓑さん”の愛称で親しまれ、古くから人々の暮らしを見守ってきた、歴史あるお社です。
淀川のほとりをお散歩しながら立ち寄れるこの神社は、日々のリズムを整えたいときや、
自然と歴史に触れてリセットしたいときにぴったりの場所。
はじまりは、神功皇后と海の物語
田蓑神社のはじまりは、なんと平安時代のはじめ。
新羅への遠征を終えた神功皇后がこの地に立ち寄り、白魚を献上した漁師の姿に感動したことがご縁だと伝えられています。
後にその漁師が再び現れ、「この神宝を大切に祀ってください」と託したのが、神社創建のきっかけ。
住吉三神と神功皇后の四柱をお祀りする「住吉四神」として、貞観十一年(869年)に創建されたと伝わっています。
東京・佃島と深いつながり
江戸時代、徳川家康公が大阪を訪れた際、ここ田蓑の漁民たちが船で渡しを務めたことがきっかけで、
家康公の関東入りに伴い、田蓑神社の神職や漁民たち34人が江戸へ移り住むことに。
そして、彼らが拓いた土地が、今も東京で有名な「佃島」。
現地には田蓑神社の御分霊を祀る神社が建てられ、ここが佃煮発祥の地として知られています。
「人のために尽くすことが、やがて自分やまちの幸せに繋がる」そんな素敵な教えが、
この地の由緒から感じられます。
震災を乗り越えて、今も変わらず
阪神・淡路大震災では、田蓑神社も大きな被害を受けました。拝殿や社務所、鳥居などが倒壊し、
参道も液状化で盛り上がるなど、多くの傷が残されました。
それでも、地元の方々の力で修復が進み、今では穏やかな境内へと復興。
境内にある復興モニュメントは、当時を忘れないための大切な記憶として、今日も参拝者を見守っています。
心を整えたい日に、ちょっとだけ立ち寄って
ご利益は、海上安全・五穀豊穣・厄除け・福徳円満など。
都会の喧騒から少し離れて、自分と向き合う静かな時間を過ごすのにもぴったりです。
川沿いをお散歩がてら、または帰り道の寄り道に。
心がふっと軽くなるような、そんなひとときを「田蓑神社」で過ごしてみませんか?
- 底筒男命
- 中筒男命
- 表筒男命
- 神功皇后
- 商売繁盛
- 交通安全
- 厄除開運
神社巡りをされる方へ|御朱印帳の選び方ガイドはこちら