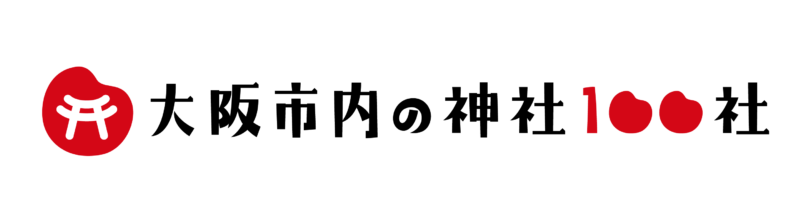キタの街に寄り添う天神さま – 綱敷天神社で願いごと日和(喜多埜天神)【大阪市・北区】

綱敷天神社(喜多埜天神)【大阪市・北区】
大阪市北区、梅田のにぎわいから少し離れた場所に佇む綱敷天神社。
平安時代の嵯峨天皇や、学問の神さま・菅原道真公ゆかりのこの神社は、静かな時間が流れる“都会の中の癒しスポット”です。
ご祭神の道真公が紅梅を愛でたというエピソードが残るこの地は、学業成就をはじめとするさまざまなご利益があるとされ、今も梅田キタの氏神さまとして多くの人々に親しまれています。
近くにはカフェやベーカリーも点在していて、おさんぽの途中にふらっと立ち寄るのにもぴったり。
キタの街に息づく歴史とやさしい空気を、ぜひ肌で感じてみてくださいね。
キタの街なかに佇む、ちょっと特別な“よりみち神社”
大阪・梅田の賑やかな街のすぐそばに、時間がゆったりと流れる不思議な場所があります。オフィスビルに囲まれながらも、ふっと空気がやわらかくなるこの場所の名は「綱敷天神社」。
都会の真ん中とは思えない静けさの中、梅や歴史に癒される、まさに“近場のお出かけ”にぴったりなスポットなんです。
嵯峨天皇ゆかりの、由緒ある神社
綱敷天神社のはじまりは、平安時代の嵯峨天皇がこの地に立ち寄られたことにさかのぼります。今の「梅田」エリアに頓宮(仮の御所)を建て、一夜を過ごされたことが神社の起源なんだとか。
天皇が亡くなられたあと、その想いを引き継いで、ゆかりの地に社殿が建てられました。それが「神野太神宮」と呼ばれ、今の綱敷天神社の原型になっています。
道真公が紅梅を愛でた、その場所に
「学問の神さま」として親しまれる菅原道真公とも、実は深いご縁があるこの神社。無実の罪で太宰府へ流される道中、道真公がこの地に咲いていた紅梅の美しさに心をとめ、船を下りて休まれたといいます。
そのとき、船を繋ぐ綱を円く敷いて即席の“座”にされ、それが「綱敷(つなしき)」という名前の由来になったんです。
梅田の「梅」は、この梅の花から?
道真公が愛でた紅梅の木。その存在が、のちに「梅田」の地名の“梅”に繋がったとも言われていて、歴史好きにはたまらない小話です。
また、道真公から名を賜った家臣たちは、彼の無事を祈ってこの地にとどまり、後に「梅塚天満宮」として小さな社を建て、代々その思いを受け継いできました。
神社とともに歩んだ街の歴史
長い時代の中で、戦火や混乱に巻き込まれたこともありましたが、不思議なことに、道真公ゆかりの御影と御綱だけは無事に残されたと伝わっています。
その後、奇跡のように一夜で松の木が7本生えたことで再建され、北野天満宮の神霊を迎えたことから、「北野村」と呼ばれるようになり、これが今の“キタ”の語源になったという説もあるんですよ。
今も変わらず、梅田キタの氏神さま
梅田が今のような大都市になっても、この地を見守り続けている綱敷天神社。通勤やお買い物で通り過ぎるあの道のすぐ近くに、静かに佇む神社があると思うと、なんだか心が和みますよね。
ご利益は学問成就だけでなく、縁結びや心願成就、商売繁盛など多岐にわたっていて、地元の人たちからも長く愛されています。
近場の癒しスポットで、心をととのえる時間を
忙しい毎日のなかでも、ちょっと立ち止まって深呼吸したいとき。綱敷天神社は、まさにそんな“近場の心のよりどころ”。
会社帰りにふらっと寄ったり、週末にカフェめぐりの途中で立ち寄ってみたり。きっと、やさしい気持ちになれる時間が待っていますよ。
癒しスポットとして、お出かけついでに、会社帰りに。ちょっと立ち止まって、心を落ち着けるひとときを過ごしてみてくださいね。
- 嵯峨天皇
- 菅原道真
- 平安豊饒
- 学業成就
- 諸願成就
綱敷天神社(喜多埜天神)
地下鉄「扇町駅」徒歩13分
地下鉄「東梅田駅」徒歩15分
神社巡りをされる方へ|御朱印帳の選び方ガイドはこちら