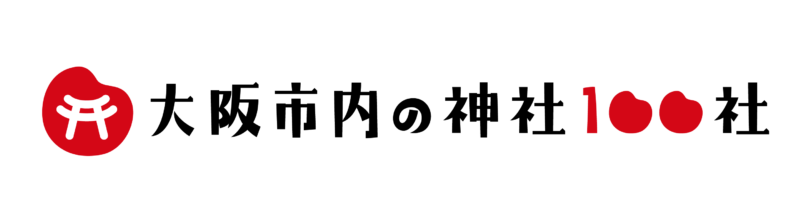江戸の面影と福のご利益にふれる下町の下之宮八阪神社(八阪神社)【大阪市・大正区】

八阪神社(下之宮八阪神社)【大阪市・大正区】
大阪市大正区に佇む「八阪神社(下之宮八阪神社)」は、歴史の面影と地域のあたたかさが感じられる、心安らぐ小さな神社。
江戸時代に創建され、厄除けや開運のご利益を授かれる場所として、長くまちに根付いてきました。
境内に足を踏み入れると、にぎやかな都市の一角とは思えないほどの静けさと清らかさ。地元の方々の暮らしに溶け込みながら、今も静かに見守り続けています。
下町らしいぬくもりと、穏やかな空気に包まれて。ふらりと立ち寄るだけで心がやわらぐ、大正区の小さな癒しスポットです。
街なかで出会う、歴史と福の神様「下之宮八阪神社」
大正区の街なかに佇む「下之宮八阪神社」は、
ちょっと懐かしい風景と、地元の人たちのぬくもりが感じられる神社です。
のんびりお散歩しながら、ふと立ち寄ってみたくなるような、
どこかほっとする空気が流れています。
神さまをお迎えしたのは、江戸の初めごろ
この神社に祀られているのは、厄除けの神さまとして知られる素盞鳴尊(すさのおのみこと)。
はじまりは、江戸時代・寛永2年(1625年)ごろと言われています。
その後、明治時代には周辺の村々から神社が合祀され、
地域の氏神さまとして、より多くの人々に親しまれるようになりました。
戦火を乗り越え、今の姿へ
昭和の初めに一度社殿が建て替えられましたが、
残念ながら、昭和20年の空襲で焼失してしまいます。
それでも、地域の人々の願いと協力によって少しずつ再建され、
昭和40年代には本殿や拝殿が整い、今の姿となりました。
節分の夜に授かる、ちょっと不思議な「宝船」
この神社の名物といえば、毎年節分の夜に行われる特別な行事。
「宝船」と呼ばれる絵巻物を笹につけて参拝者に授けるという、ちょっとユニークな風習です。
枕の下にこの宝船を敷いて眠り、吉夢を見たら一年安泰。
凶夢だったら川に流す…という、昔ながらのロマンあるおまじない。
この風習は、江戸時代に栄えた北前船(きたまえぶね)の伝承にちなんでいるのだそう。
当時、大阪港に米を運んできた北前船は、三軒家では「宝船」とも呼ばれ、
たくさんの恵みをもたらしてくれた存在でした。
下町の風情と、ほっとする静けさを感じに
都会のにぎわいから少し離れて、下町の空気に包まれてみませんか?
歴史と人々の想いが重なり合う「下之宮八阪神社」は、
近所のお散歩途中に、ふと立ち寄りたくなるような、あたたかい場所です。
- 素盞嗚尊
- 応神天皇
- 仁徳天皇
- 菅原道真
- 相殿天照皇大神
- 弥都波能売神
- 春日大神
神社巡りをされる方へ|御朱印帳の選び方ガイドはこちら