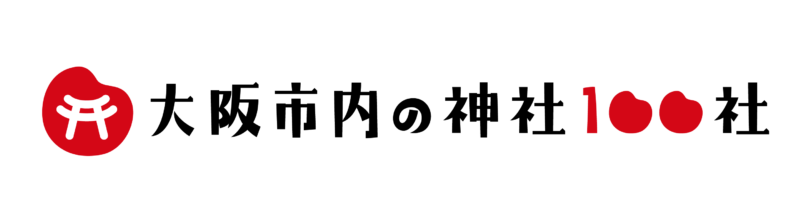樹齢400年の楠に癒される – 東淀川の天神さん(菅原天満宮)【大阪市・東淀川区】

菅原天満宮【大阪市・東淀川区】
大阪市東淀川区に佇む菅原天満宮は、地域にやさしく寄り添う“町の天神さま”。
江戸時代から続く「砂持ち神事」や、樹齢400年を超えるクスノキが印象的で、昔ながらのぬくもりが息づいています。
学業成就などのご利益を求めて訪れる人も多く、境内では季節ごとの風の香りを感じながら、心静かなひとときを過ごせます。
ふと日常の合間に、自分を整えたくなったら、ふらっと立ち寄りたい場所です。
地元に根ざしたこの区の神社で、やさしい時間を感じてみてください。
歴史とやさしさに包まれる、町の天神さま
大阪市東淀川区にある「菅原天満宮」は、地域に寄り添うように佇む小さなお社。
地元の方々からは “天神さん” と呼ばれ、今も昔も、変わらず親しまれています。
駅からふらっと歩ける距離にありながら、
一歩境内に足を踏み入れると、まるで時間がゆっくり流れはじめるような心地よさ。
穏やかな木々の揺れと、古くからの風習が息づく空間が、訪れる人の心をそっと整えてくれます。
地元の人々に守られてきた天神さん
神社がこの地に創建されたのは、今から約400年前の寛永年間。
長い歴史の中では天災に見舞われ、古い記録は残っていないものの、
天保13年には社殿が再建され、そして昭和43年には現在の本殿と拝殿が新築されました。
境内は少し高くなっていて、石段を上がると見晴らしのいい小丘にたどり着きます。
この高台は、実は“土を運び積み重ねた”歴史がある場所なんです。
大切に受け継がれる「砂持ち神事」
江戸時代の天保のころ。堤防を守るため、毎年9月9日に地域の人々が集まり、
土を運んで神社の境内に積む「土持ち」の風習が生まれました。
「砂持ちせんものは鼻黒や」なんて、ちょっとユーモラスな言い回しで、
村の人みんながこの行事に参加したそうです。
今でもこの伝統は「砂持ち神事」として残っていて、
10月の例祭には、近くの園児たちが小さな手で砂を運び、神さまと心をつなぐ微笑ましい風景が見られます♡
樹齢400年の楠と、菅公の伝説
境内で圧倒的な存在感を放つのは、樹齢約400年、高さ18mにもなる大きなクスノキ。
大阪市の保存樹にも指定されていて、まさにこの地のシンボルとも言える存在です。
さらに境内の下には「牛まわし」の石碑も。
これは、学問の神さまとして知られる菅原道真公が太宰府へと旅立つ途中、
この地でひと休みされた際、村人たちが牛を引いてぐるりと慰めたという心あたたまるエピソードから生まれたもの。
日常の合間に、心を整える場所
高いビルが並ぶ街の中で、静かに息づく菅原天満宮。
学業成就や心願成就を祈願する人はもちろん、
ただふらっと訪れても、自然と心が落ち着く優しい場所です。
季節ごとに風の表情も変わるこのお社で、
ちょっとだけ、日常の足をとめてみませんか?
- 菅原道眞公
- 宇迦御魂神
- 厄除開運
- 学業成就
- 除災招福
神社巡りをされる方へ|御朱印帳の選び方ガイドはこちら