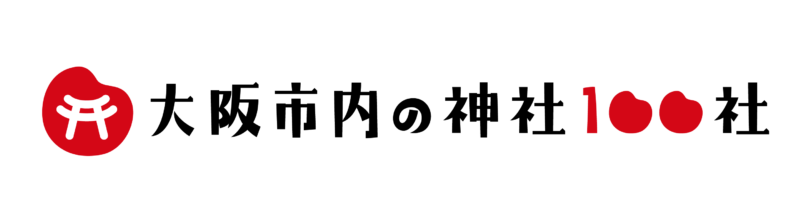十三の街で心ほどける時間 – 神津神社で願いを届けよう【大阪市・淀川区】

神津神社【大阪市・淀川区】
阪急十三駅から徒歩すぐ。淀川区のまちに長く寄り添う「神津神社」は、地域の守り神として親しまれてきた静かな神社です。
そのはじまりは戦国時代。7つの村の神さまをひとつにおまつりするかたちで生まれたこの神社は、地元に根づく“絆”の象徴として、今も大切に守られています。
境内にはやさしい風がそよぎ、日常のあわただしさを忘れさせてくれるような、心が整う場所。十三のまち歩きの途中や、ちょっと気分をリセットしたい日に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
家内安全や商売繁盛、交通安全など、身近な願いにそっと寄り添ってくれる神津神社で、あなたもやさしいひとときを感じてみてください。
十三のまちに寄り添う、地域の守り神
阪急十三駅から少し歩いた先に、やさしい空気をまとう神社があります。
その名も「神津神社(かみつじんじゃ)」。十三や三国、野中、新高など、淀川区の広い地域を見守ってきた、地元の鎮守さまです。
高層ビルや商店街が並ぶ都会の風景の中に、ふと現れる静かな境内。
近くに住んでいても、こんな落ち着く場所があったなんて…そんなふうに感じる人もきっと多いはず。
はじまりは、天正年間の八幡さま
神津神社のルーツは、戦国時代の天正年間(1570年代頃)までさかのぼります。
当時すでにこの地に「八幡神社」として鎮座し、村人たちの心のよりどころとなっていました。
境内から見つかった棟札には、江戸時代に再建された記録も残っていて、
440年以上もの歴史を重ねてきたことがわかっています。
7つの村がひとつになって、「神津神社」に
時が流れて明治42年。小島、木川、野中、新在家、堀上、今里、堀、この地域にあった7つの村が協議のうえ、
それぞれの神社を合祀して生まれたのが「神津神社」という新たな名の神社です。
神さまたちがひとつに集まったこのお社は、まさに地域の“絆の象徴”ともいえる存在。
それから今に至るまで、地域に根ざしたおまつりや参拝が大切に守られています。
毎年1月の「十三戎」は商売繁盛の福の神
お正月の風物詩、「十三戎(じゅうそうえびす)」も神津神社の名物です。
昭和30年に今宮戎神社から御分霊をいただき、商売繁盛の神さまとして信仰されるようになりました。
1月9・10・11日の三日間、福笹や縁起物を授かりにたくさんの参拝客でにぎわいます。
十三駅からも近いので、仕事帰りにふらっと立ち寄る人も多いんですよ♡
昔と今が重なる、ほっとできる場所
神津神社のあるあたりは、江戸時代から焼き物で知られた「吉向窯」があった土地。
歴史の香りを残すこのまちは、今もどこか懐かしさを感じさせてくれます。
社殿も昭和に建て替えられ、現在の姿に。街の変化に寄り添いながら、静かに時を刻んでいます。
ゆったりと、心が整う時間を
神津神社は「家内安全」「商売繁盛」「交通安全」など、日々の暮らしに寄り添うご利益で知られています。
近くにいるからこそ、ふとしたときに立ち寄れる“心の拠り所”。
街歩きの途中に、仕事帰りに、そして大切な願いを込めたいときに。
ぜひ、神津神社で心を整える時間を過ごしてみてください。
- 応神天皇
- 神功皇后
- 底筒男命
- 中筒男命
- 表筒男命
- 外四柱
- 家内安全
- 商売繁盛
- 厄除開運
神社巡りをされる方へ|御朱印帳の選び方ガイドはこちら