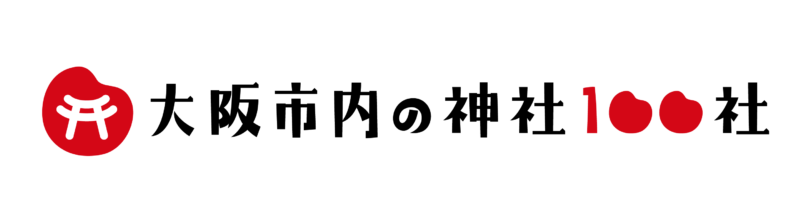千年の歴史が息づく平野の杭全神社で深呼吸 杭全神社【大阪市・平野区】

杭全神社【大阪市・平野区】
大阪市・平野区にある杭全神社(くまたじんじゃ)は、千年以上の歴史を持つ由緒ある神社。地域の方からも親しまれており、平野のまち歩きの途中にふらっと立ち寄れる、落ち着いた空気が漂うお社です。
平安時代、まちづくりを担った武将によって創建されたこの神社は、「祇園社」としてスタート。その後、熊野信仰が加わることで、今では三殿にそれぞれ異なる神さまが祀られ、多様なご利益がいただける神聖な場所として信仰を集めています。
境内には、光を放ったという伝説が残る松の木の話や、かつての「熊野権現」「祇園宮」としての歴史も感じられ、ロマンをくすぐられます。
日常のなかで、静かに自分と向き合いたいとき。歴史や伝説に触れながら、心を落ち着けられる時間が、杭全神社にはあります。平野区を歩くときは、ぜひ一度立ち寄ってみてくださいね。
平野のまちに息づく、歴史ロマンあふれる「杭全神社」
大阪・平野のまちなかに佇む「杭全神社(くまたじんじゃ)」。
ゆったりとした空気が流れるこの神社、実は千年以上の歴史を持つ、由緒あるお社なんです。
通りを歩いていてふと現れる立派な鳥居と、重厚感ある社殿。
近くにありながら、少しタイムスリップしたような気持ちになる、そんな場所です。
始まりは、武将のまちづくりから
時は平安時代。征夷大将軍・坂上田村麿の子である広野麿がこの地に荘園を築き、
その子・当道(まさみち)によって、京都から牛頭天王(ごずてんのう)をお招きし、氏神として祀られたのが杭全神社の始まりです。
当時は「祇園社」と呼ばれていたこの神社。やがて熊野信仰が広まると、熊野の神様も迎え入れられ、
3つの本殿にそれぞれ異なる神様が祀られる、神聖な場となっていきました。
伝説の松の木と光の奇跡
熊野の神様を迎えるきっかけとなったのは、ある不思議なできごと。
山伏が神様の姿を彫った尊像を神社に奉納しようとしたところ断られ、松の木に背負子(おい)をかけて立ち去ったのだとか。
するとその夜、松の木から光が放たれたり、不思議な現象が次々と起こり…
ついには社殿が建てられ、多くの人々が集まる信仰の場となったそうです。
「熊野権現」「祇園宮」ふたつの顔を持つ神社
後醍醐天皇の勅命を受けて建立された第二殿には、熊野三所権現が祀られています。
かつては「熊野権現」「祇園宮」と並び称され、今もその名残が町の道しるべとして残っています。
明治時代には、かつての地名「杭全荘」にちなんで「杭全神社」と改称されました。
街を見守り続ける、平野のシンボル
神社のあるこの地域、かつては「杭全荘」と呼ばれていましたが、やがて「平野(ひらの)」へ。
江戸時代には独自の自治も行われ、町として大きく発展しました。
今も氏子地域は平野区と東住吉区にまたがっており、地域の守り神として人々の暮らしに寄り添い続けています。
夏が待ち遠しくなる、だんじり祭り
毎年7月11日〜14日に行われる夏祭は、平野名物の「だんじり曳行」が見もの。
本郷エリアから9台、散郷から1台のだんじりが登場し、熱気と賑わいで町中が活気に包まれます。
30万人もの人が訪れると言われるこのお祭りは、まさに“夏の風物詩”。
夜には幻想的な灯りに包まれ、地域の絆を感じる時間となります。
日常の中で、ふと立ち寄りたい静かな時間
国の重要文化財にも指定された本殿三棟は、見上げるだけで歴史の重みが感じられます。
そんな静かな空間で、ゆったり深呼吸するだけで気持ちが整う…そんな不思議な力を持つ場所。
会社帰りに、週末のお散歩に、平野のまち歩きの途中に。
ぜひ杭全神社で、ちょっとだけ時の流れをゆっくり感じてみてくださいね。
- 素盞鳴尊
- 伊弉冊尊
- 速玉男尊
- 事解男尊
- 伊弉諾尊
- 攘災招福
- 家内安全
神社巡りをされる方へ|御朱印帳の選び方ガイドはこちら